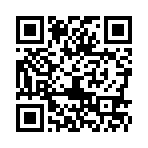2012年03月28日
(4)進む協業化<上>養殖と漁船、役割分担成功
(河北新報 1月26日) 三陸の浜では、協業化に対する抵抗感が依然、根強い。 協業化で新たな漁業に挑戦する西日本の先進地3カ所を取材し、 収益性向上やブランド化、後継者確保などのメリットを検証。 <1億円を突破> 薩摩半島西端にある鹿児島県南さつま市の野間池漁港は、 鹿児島弁で、「すんくじら(隅っこ)」と呼ばれる人口200余の小さな漁村。 9年前に発足した協業体のマグロ養殖は2010年度、売上高1億円の大台を突破。 「養殖マグロは、しばらく売り手市場が続く。2億円はいける」。 野間池マグロ養殖協業体の代表森剛さん(48)は、余裕の表情。 夏場、野間岬の沖合に来遊する天然のクロマグロ(ホンマグロ)の稚魚「ヨコワ」を 漁獲し漁港内のいけす8基へ投入。 小魚の生き餌を2、3年与え、丸々と太らせる。 スーパーなど小売りのニーズに応じ、40kg前後に成長した時点で水揚げ。 全量を流通業者と相対で取引し、空輸便で東京・築地をはじめ首都圏の卸売市場に届ける。 鹿児島県は、国内生産量の3割強を占める最大の養殖マグロ拠点。 大手水産会社の系列企業もしのぎを削る中、全員が地元の漁業者で構成される野間池は、 協業化の輝かしい成功事例。 <バブル後 窮地> 野間池では戦後、ハマチ、カンパチの養殖が盛んになったが、 バブル経済崩壊の前後から、魚価の長期低落傾向が続いてきた。 高値がついた養殖カンパチも同業者が増え、浜値は1kg当たり1000円を切る。 燃料・飼料代の高騰も、追い打ちを掛けた。 協業体の取り組みを支援する南さつま漁協参事の森晃さん(57)は、 「浜から船がなくなり、人もいなくなった」と振り返る。 この地域では、東京の社団法人が1990年代前半からマグロの試験養殖を実施。 法人や漁協が事業の引き受け手を探していたところ、 カンパチ養殖の実績があった森剛さんが名乗りを上げた。 新たなマグロ養殖への挑戦に当たり、森剛さんが着目したのが協業化という手法。 野間池の協業体の構成メンバーは、現在16人。 森剛さんら9人の養殖業者と、7人の漁船漁業者のジョイントビジネス。 漁船漁業者は、ヨコワを1匹3500円で養殖業者に提供。 <若者の定住も> マグロ養殖は、良質な稚魚の確保が成否を左右。 「漁船漁業者は、閑漁期の夏場に収入が増えるメリットがあり、 養殖業者には、稚魚の安定的な入手にめどが立つ。 両者の利害が一致した」と森剛さん。 協業化は、雇用拡大という果実も生んだ。 野間池には、県内外から30代後半の若者3人が新規参入。 養殖業の即戦力になっているだけでなく、にぎわいの消えた浜を活気づけた。 野間池の協業化を調査している鹿児島大の鳥居享司准教授(漁業経済学)は、 「マグロ養殖は、個人では到底無理だが、漁業者間の役割分担と協力によって可能に。 若者の定住まで促した協業化が地域に与えた影響は大きい」と評価。 http://blog.kahoku.co.jp/saisei/2012/01/post-14.html
Posted by wmvxbdglvb at 11:43│Comments(0)